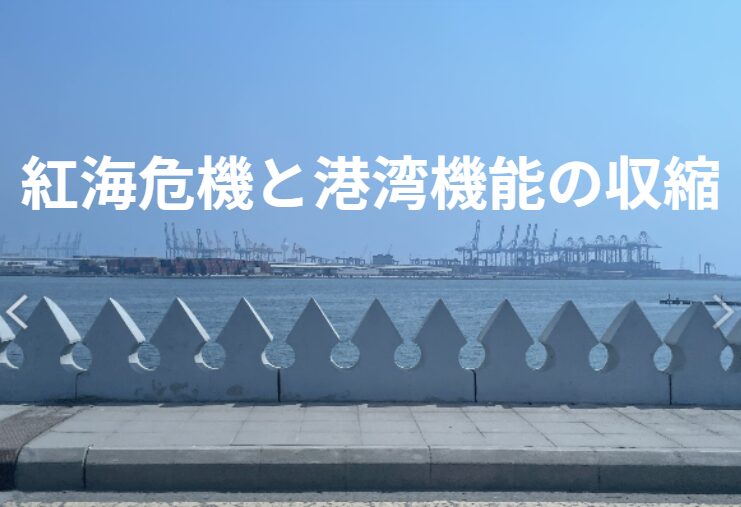2023年秋以降、イエメンのフーシ派がバブ・エル・マンデブ海峡周辺で商船攻撃を継続したことで、紅海~スエズ運河の主要動脈は構造的な混乱に陥った。海運各社は安全確保を最優先に喜望峰まわりの迂回航行へ切り替え、アジア—欧州/地中海—中東の広域ネットワークで航走日数の伸長・コスト増・配船再編がドミノのように連鎖した。2025年7月時点の業界更新でも、主要船社の紅海/スエズ回避と喜望峰迂回が常態化したと整理されている。これによりコンテナ船の輸送日数は大幅に増え、海上ルートの混乱と運賃の混乱が生じた。
この長期化は、単なる遅延にとどまらず、通行料・燃料費・保険料(戦争危険保険)の上振れ、コンテナ循環の乱れ、船腹の拘束日数増を通じて、広範なサプライチェーン・コスト構造を押し上げた。とりわけエジプトのスエズ運河収入は急減し、当局は流入回復へ通航料割引の検討に踏み出すなど、国家財政面にも打撃が波及している。
紅海の「安全度」は月次ベースでも改善が見えにくい。英国海運貿易運用(UKMTO)の通報では2025年7月時点でも新規事案が発生しており、航行リスクの残存が裏づけられる。結果として、荷主・フォワーダーは**海上単独から海空複合(Sea–Air)**へのシフト、在庫水準の上積み、寄港地やハブの切り替えなど、レジリエンス確保のための運用設計を迫られている。
この連続波が最も鋭く突き刺さったのが、イスラエル唯一の紅海港・エイラートだ。2023年末以降の航路敬遠により、車両・原油・家畜などの取扱いが蒸発的に減少。港湾活動は9割落ち込み、19か月に及ぶ赤字で経営は臨界点に達した。2025年7月16日、港湾会社は**7月20日での業務停止(閉鎖)**を発表。地域情勢に起因する航路遮断の「最後の一押し」で、港は事実上ストップに追い込まれた。
物流への一次影響は明快だ。①リードタイム延伸:アジア—地中海基幹航路で往復2~3週間規模の増加が常態化、需給が締まりやすくなり割増運賃が断続的に発生。②在庫運用の難度上昇:補充リード長期化により安全在庫の再設計が必要。③ハブ・ルーティングの再編:紅海—東地中海の直結性低下を受け、ペルシャ湾/欧州北部/アフリカ南端経由への系統替えが進む。④保険・付帯費用の高止まり:高リスク水域指定に伴う保険料・サーチャージが価格に転嫁されやすい。これらは製造・小売の調達原価、最終消費者価格、在庫回転に連鎖し、海運市況の変動幅も拡大させる。
二次影響としては、スエズを経由しない迂回の恒常化が運河収入を直撃し、周辺国の外貨収入・港湾投資計画にも影を落とす。また、輸送の遅延・コスト増が航空・Sea–Airへ一部需要をスライドさせ、ハイテク・高付加価値品ではモーダルミックスが進む。一方で、海運側は**配船融通(スライド・ブランキング)や臨時GRIで需給を調整、平時よりも「運用設計の巧拙」**がコスト差に直結する局面が続いている。
まとめ:当面の実務ポイント
- ルート多様化:紅海回避を前提に、喜望峰周り・欧州北部経由・湾岸ハブ活用の複線化を常設化。
- 在庫政策:補充リード+安全在庫の再計算、SKUごとのサービス水準の見直し。
- 契約ポートフォリオ:スポット/長期のミックス最適化、戦争危険・割増費の扱い条件を明文化。
- リスク監視:UKMTO等の海域アラート常時監視とBCP更新、Sea–Air切替の発動基準を明確化。
紅海危機は「一過性の遅延」から「ネットワーク再設計を迫る構造変化」へと段階を進めた。エイラート港の休止はその象徴であり、安全・コスト・納期の三立をどう図るかが、今後の国際物流における競争力の分水嶺となる。今後の行方を確認しながら並行して輸送ルートや調達国の再調整も視野にいれる必要がでてくる。